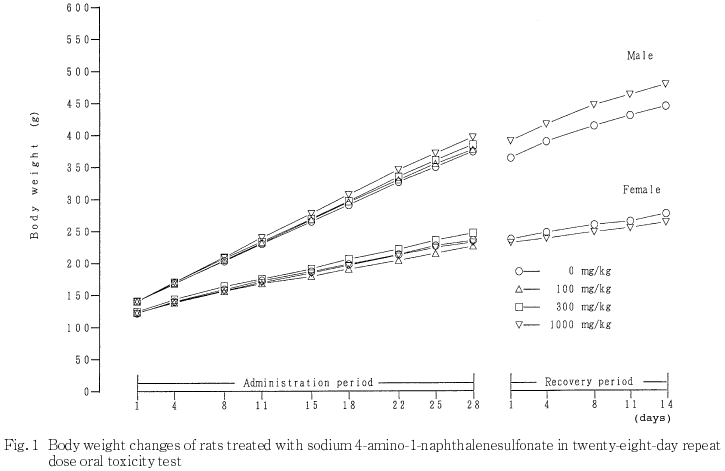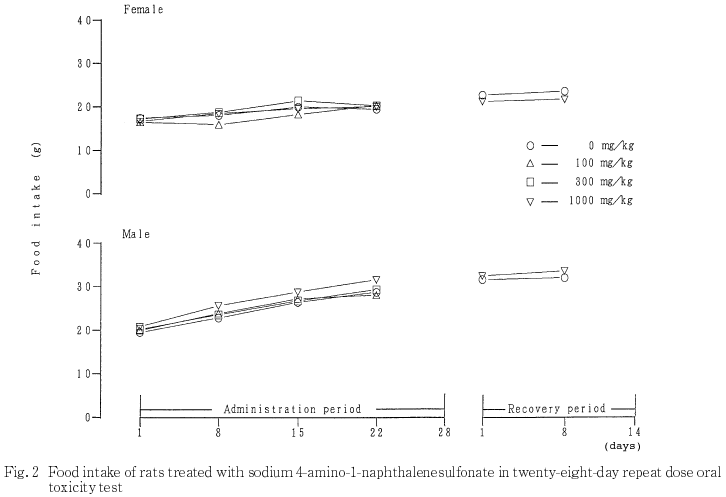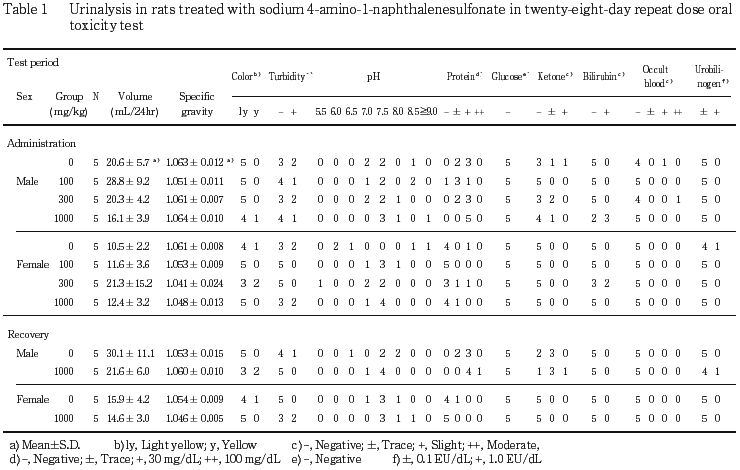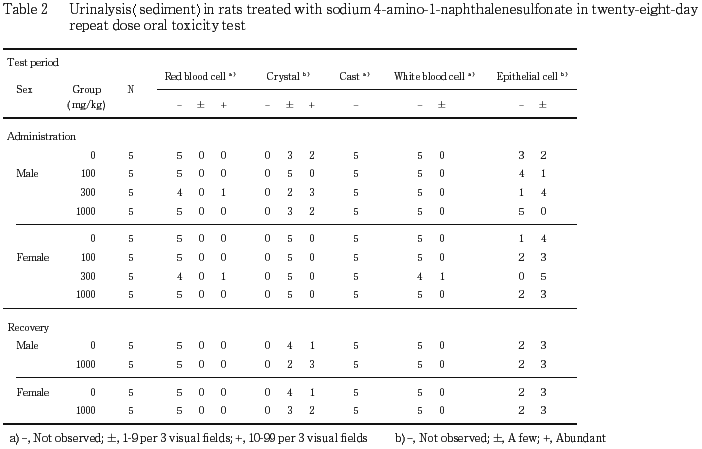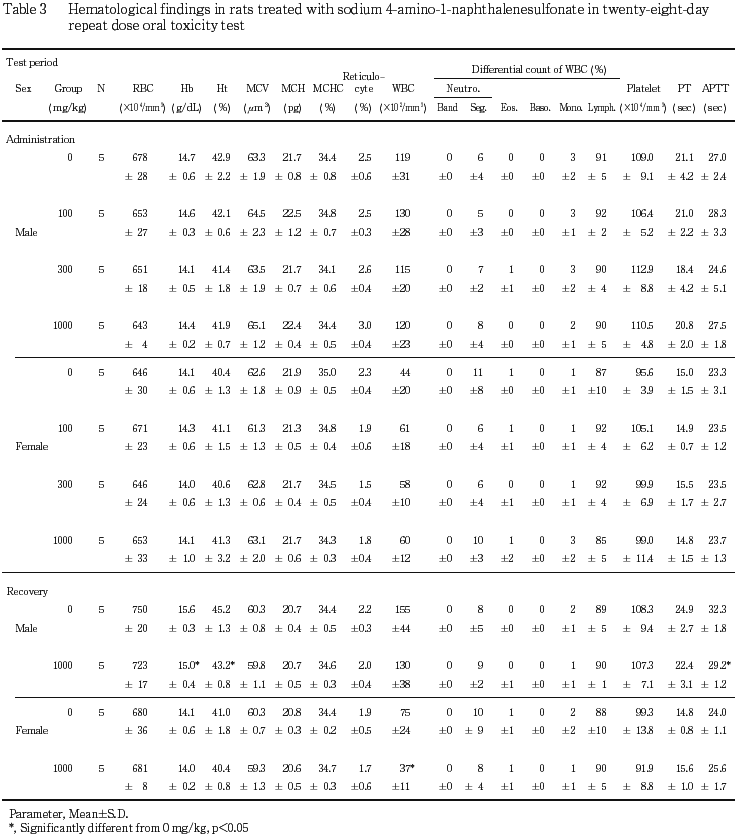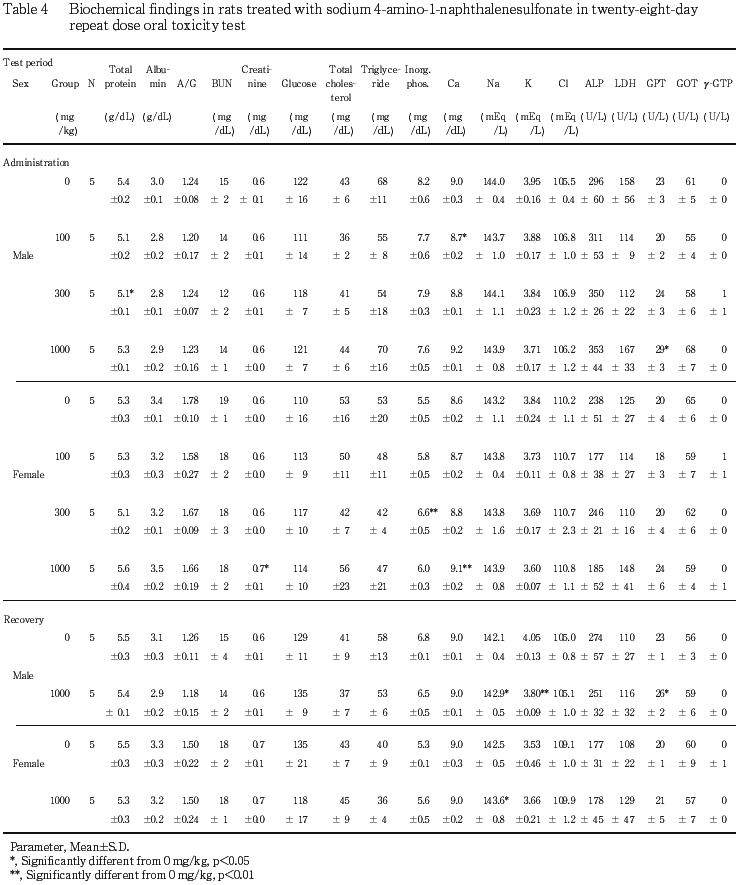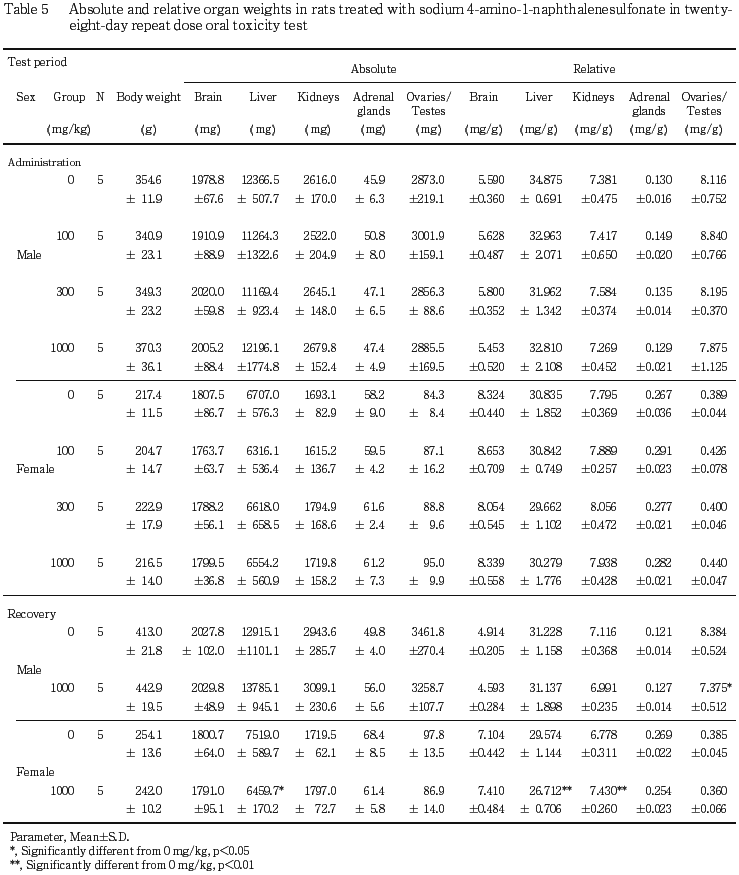4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウムのラットを用いる
28日間反復経口投与毒性試験
Twenty-eight-day Repeat Dose Oral Toxicity Test of
Sodium 4-amino-1-naphthalenesulfonate in Rats
要約
4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウムの28日間反復経口投与毒性試験(回復14日間)を雌雄のSprague-Dawley系(Crj:CD)ラットを用いて実施した.投与量は,雌雄とも0(溶媒対照群),100,300および1000 mg/kgとした.雌雄とも溶媒対照群および1000 mg/kg投与群では1群10匹,100および300 mg/kg投与群では1群5匹を使用し,このうち溶媒対照群および1000 mg/kg投与群の雌雄各5匹で14日間の回復試験を行った結果,以下の成績を得た.
投与期間中および回復試験期間中に,いずれの投与群においても死亡例は認められず,一般状態,体重,摂餌量および尿検査,血液学検査,病理学検査の結果にも被験物質投与に起因したと考えられる変化はみられなかった.
一方,投与期間終了時における血液生化学検査では,雌雄の1000 mg/kg投与群のGPT活性に高値が認められ,被験物質投与に起因した所見である可能性が高いと判断された.
以上の結果から,本試験条件下における4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウムの無影響量は,雌雄とも300 mg/kgであると判断した.
方法
1. 被験物質および投与検体の調製
被験物質として,スガイ化学工業 より提供された4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウム〔ロット番号:6622,分子量:245.24,淡紫色粉末,純度:76.1 %(w/w)〕を用い,入手後,室温遮光条件下にて保管した.
より提供された4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウム〔ロット番号:6622,分子量:245.24,淡紫色粉末,純度:76.1 %(w/w)〕を用い,入手後,室温遮光条件下にて保管した.
被験物質を20 %(w/v)の濃度になるよう日局注射用水〔製造番号:9510AH,光製薬 〕に溶解し,さらに,この20 %溶液を6および2 %(w/v)濃度となるように段階希釈して調製した後,褐色瓶に分注し,冷暗所に保管した.投与検体は,前日に冷暗所から取り出し,室温にもどしてから使用した.投与検体の調製は4あるいは6日間に1回の頻度で行った.なお,調製検体の安定性試験および含量試験を実施した結果,0.2および20.0 %(w/v)溶液中の被験物質は,冷暗所での6日間と,それに続く室温24時間は安定であり,また,投与検体中の被験物質の含量は,所定濃度の102〜105 %であることが確認された.
〕に溶解し,さらに,この20 %溶液を6および2 %(w/v)濃度となるように段階希釈して調製した後,褐色瓶に分注し,冷暗所に保管した.投与検体は,前日に冷暗所から取り出し,室温にもどしてから使用した.投与検体の調製は4あるいは6日間に1回の頻度で行った.なお,調製検体の安定性試験および含量試験を実施した結果,0.2および20.0 %(w/v)溶液中の被験物質は,冷暗所での6日間と,それに続く室温24時間は安定であり,また,投与検体中の被験物質の含量は,所定濃度の102〜105 %であることが確認された.
2. 動物および飼育方法
生後4週で購入した雌雄のSprague-Dawley系ラット(Crj:CD;SPF,日本チャールス・リバー )を6日間にわたり予備飼育した後,一般状態に異常の認められなかった雌雄各30匹を試験に供した.動物は,全飼育期間を通じて,温度24.0〜25.5℃,湿度44〜64 %,換気回数約15回/時間,照明12時間(7〜19時点灯)に制御された飼育室内で,金属製金網床ケージに1匹ずつ収容し,固型飼料(CE-2,日本クレア
)を6日間にわたり予備飼育した後,一般状態に異常の認められなかった雌雄各30匹を試験に供した.動物は,全飼育期間を通じて,温度24.0〜25.5℃,湿度44〜64 %,換気回数約15回/時間,照明12時間(7〜19時点灯)に制御された飼育室内で,金属製金網床ケージに1匹ずつ収容し,固型飼料(CE-2,日本クレア )および水道水(秦野市水道局給水)を自由に摂取させて飼育した.
)および水道水(秦野市水道局給水)を自由に摂取させて飼育した.
3. 群および群分け
投与量は,本試験開始前に予備試験として秦野研究所で実施した4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウムのラットにおける7日間反復経口投与毒性試験の成績を参考にして決定した.即ち,雄のSprague-Dawley系ラットに4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウムを100,300および1000 mg/kgの用量で7日間反復投与した結果,死亡例はなく一般状態にも変化は認められなかった.また,剖検においても,被験物質投与に起因すると思われる異常所見は認められなかった.以上の結果から,本試験では,化審法ガイドライン「ほ乳類を用いる28日間の反復投与毒性試験」に従って,雌雄とも最高投与用量を1000 mg/kgとし,以下公比約3で除し,中および低用量には300および100 mg/kg投与群を設定した.なお,雌雄とも溶媒対照群には日局注射用水のみを経口投与した.
群分けは,検疫期間中に異常のない動物の中から,投与開始前日の体重に基づいて,体重別層化無作為抽出法により行った.動物数は,溶媒対照群および1000 mg/kg投与群では,雌雄各群10匹とし,100および300 mg/kg投与群では,各5匹の動物を用いた.また,溶媒対照群および1000 mg/kg投与群では,各群5匹を投与期間終了後,14日間の回復試験に用いた.
4. 投与方法
投与経路は,化審法ガイドライン「ほ乳類を用いる28日間の反復投与毒性試験」に従い経口投与とした.
投与は,1日1回,28日間,毎日9時〜12時の間に,ラット用胃管を用いて強制的に行い,投与液量は,雌雄とも5 mL/kgとして,各投与時に最も近い時点で測定された体重に基づいて個別に算出した.
5. 検査項目
1) 一般状態の観察
投与期間および回復試験期間を通じて,毎日,死亡例の有無を調べた.また,全例について,一般状態を投与期間中は毎日,投与前および投与後の1日2回(回復試験期間中は1回)観察した.
2) 体重および摂餌量の測定
投与開始週では,投与開始直前と投与第4日,第2週以降の投与期間および回復試験期間中は,全例について1週に2回の頻度で体重を測定し,投与期間あるいは回復試験期間終了日および剖検日にも体重の測定を行った.また,投与開始週では,投与開始日に,第2週以降の投与期間および回復試験期間中は,全例について,1週に1回の頻度で1日当たりの摂餌量の測定を行った.
3) 尿検査
投与期間終了週(投与第23日)に各群とも動物番号の若い方から5匹を選択し,また回復試験期間終了週(回復第9日)には回復試験例全例を,いずれも約24時間代謝ケージに収容して採尿し,尿量〔天秤で計量(尿重量を比重で除す)〕,色調および混濁(視診),比重〔重量法,使用天秤(AE200,メトラー)〕について検査した.なお,pH, 潜血, 蛋白質, 糖, ケトン体, ビリルビン, ウロビリノーゲンおよび沈渣の検査は, 代謝ケージに収容して約4時間以内に採取した尿について,試験紙法(マルティスティックス/クリニテック 200,バイエル三共)および鏡検(光学顕微鏡)によって実施した.
4) 血液学検査
投与期間終了時および回復試験期間終了時の剖検に先立ち,全例について,18ないし24時間絶食させたのち,ペントバルビタール麻酔下で腹部後大静脈よりEDTA-2Kを抗凝固剤として採血し,Coulter Counter(Model S-PLUS  ,コールターエレクトロニクス)により赤血球数(電気抵抗法),白血球数(電気抵抗法),血色素量(吸光度法),平均赤血球容積(電気抵抗法),および血小板数(電気抵抗法)を測定し,これらを基に平均赤血球血色素量,平均赤血球血色素濃度およびヘマトクリット値を算出した.また,血液の一部は塗抹標本とし,白血球分類(Wright-Giemsa染色)および網状赤血球比率(Brecher法)を求めた.なお, プロトロンビン時間および活性部分トロンボプラスチン時間の測定には, クエン酸ナトリウムを抗凝固剤として採血した血液を用いて,光散乱検出法(CA-3000,東亜医用電子
,コールターエレクトロニクス)により赤血球数(電気抵抗法),白血球数(電気抵抗法),血色素量(吸光度法),平均赤血球容積(電気抵抗法),および血小板数(電気抵抗法)を測定し,これらを基に平均赤血球血色素量,平均赤血球血色素濃度およびヘマトクリット値を算出した.また,血液の一部は塗抹標本とし,白血球分類(Wright-Giemsa染色)および網状赤血球比率(Brecher法)を求めた.なお, プロトロンビン時間および活性部分トロンボプラスチン時間の測定には, クエン酸ナトリウムを抗凝固剤として採血した血液を用いて,光散乱検出法(CA-3000,東亜医用電子 )により測定した.
)により測定した.
5) 血液生化学検査
前述の血液学検査のための採血に引き続き,ヘパリンを抗凝固剤として採血し,それぞれ血漿を分離して遠心方式生化学自動分析装置(COBAS-FARA,ロシュ)により, 総蛋白濃度(ビウレット法),アルブミン濃度(BCG法),総コレステロール濃度(COD・DAOS法),ブドウ糖濃度(グルコキナーゼ・G6PDH法),尿素窒素濃度(ウレアーゼ Gl.DH法),クレアチニン濃度(Jaff 法),アルカリフォスファターゼ活性(パラニトロフェニルリン酸基質法),GOT活性(SSCC法),GPT活性(SSCC法),LDH活性(Wr
法),アルカリフォスファターゼ活性(パラニトロフェニルリン酸基質法),GOT活性(SSCC法),GPT活性(SSCC法),LDH活性(Wr blewski-La Due法),カルシウム濃度(OCPC法),無機リン濃度(モリブデン酸直接法),トリグリセライド濃度(GPO・DAOS法),γ-GTP活性(γ-グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリド基質法),A/G比(総蛋白濃度およびアルブミン濃度より算出)を測定した.また,全自動電解質分析装置(EA05,A&T)により,ナトリウム濃度(イオン電極法),カリウム濃度(イオン電極法),塩素濃度(イオン電極法)を測定した.
blewski-La Due法),カルシウム濃度(OCPC法),無機リン濃度(モリブデン酸直接法),トリグリセライド濃度(GPO・DAOS法),γ-GTP活性(γ-グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリド基質法),A/G比(総蛋白濃度およびアルブミン濃度より算出)を測定した.また,全自動電解質分析装置(EA05,A&T)により,ナトリウム濃度(イオン電極法),カリウム濃度(イオン電極法),塩素濃度(イオン電極法)を測定した.
6) 病理学検査
前述の採血に引き続き,必要に応じて腋窩動脈を切断して放血屠殺したのち,器官および組織の肉眼的観察を行った.また,各動物の脳,肝臓,腎臓,副腎,精巣または卵巣の重量測定を行い,各器官重量を剖検日の体重で除して,それぞれの相対重量を算出した.さらに,脳,脊髄,下垂体,眼球,ハーダー腺,甲状腺(上皮小体を含む),顎下腺(舌下腺を含む),心臓,肺,肝臓,腎臓,脾臓,膵臓,副腎,胃,十二指腸,空腸,回腸,結腸,直腸,精巣または卵巣,精嚢腺,膀胱,前立腺,骨髄(大腿骨),坐骨神経,骨格筋(下腿部)および病変部については,0.1 Mリン酸緩衝10 %ホルマリン液(pH 7.2)で固定した.病理組織学検査は,投与期間終了時の剖検動物のうち1000 mg/kg投与群および溶媒対照群の脳,脊髄,心臓,肝臓,腎臓,脾臓,副腎,坐骨神経について,パラフィン包埋後,ヘマトキシリン・エオジン染色標本を作製して実施した.また,投与期間終了時および回復試験期間終了時の剖検時に肉眼的に異常が認められた動物の病変部についても実施した.
6. 統計処理法
体重,摂餌量,尿検査(尿量,比重)および定期解剖例の血液学検査,血液生化学検査ならびに器官重量の値について,各群ごとに平均値および標準偏差を求めた.また,試験群の構成が溶媒対照群を含め3群以上ある場合は,Bartlettの方法による分散の一様性の検定(有意水準:5 %)を行い,ついで,分散が一様な場合は,一元配置型の分散分析を行い,有意(有意水準:5 %)の時はDunnettあるいはScheff 法方法で多重比較を行った.一方,分散が一様でない場合はKruskal-Wallisの順位検定を行い,有意(有意水準:5 %)ならばDunnett型あるいはScheff
法方法で多重比較を行った.一方,分散が一様でない場合はKruskal-Wallisの順位検定を行い,有意(有意水準:5 %)ならばDunnett型あるいはScheff 法の方法で多重比較を行った.また,試験群が溶媒対照群を含め2群となる場合には,溶媒対照群と被験物質投与群の各平均値の差の検定は,等分散であればStudentのt検定,不等分散であれば,Aspin-Welchのt検定を行った.さらに,病理組織所見については,グレード分けしたデータはMann-WhitneyのU検定により,また,陽性グレードの合計値はFisherの直接確率の片側検定により,溶媒対照群と各被験物質投与群との間の有意差検定を行った(有意水準:5 %).
法の方法で多重比較を行った.また,試験群が溶媒対照群を含め2群となる場合には,溶媒対照群と被験物質投与群の各平均値の差の検定は,等分散であればStudentのt検定,不等分散であれば,Aspin-Welchのt検定を行った.さらに,病理組織所見については,グレード分けしたデータはMann-WhitneyのU検定により,また,陽性グレードの合計値はFisherの直接確率の片側検定により,溶媒対照群と各被験物質投与群との間の有意差検定を行った(有意水準:5 %).
結果
1. 一般状態
一般状態の変化として,投与期間中の溶媒対照群において,雄の1例に頸部の皮膚に痂皮,潰瘍および脱毛が,回復試験期間中でも痂皮,脱毛がみられ,他の雄の1例では,投与期間および回復試験期間を通じて,両前肢に脱毛が認められた.さらに,雌の1例では,投与期間中,頸部の皮膚に痂皮が,回復試験期間中では痂皮,潰瘍,脱毛がみられた.また,投与期間中,1000 mg/kg投与群では,雄の2例に頸部の皮膚に痂皮がみられ,そのうちの1例には潰瘍もみられた.さらに,同群の雌の1例では,投与第19日に投与後の一過性の流涎が認められた.
2. 体重(Fig. 1)
投与期間および回復試験期間を通じて,雌雄ともに溶媒対照群と被験物質投与群との間で平均体重に有意差は認められなかった.
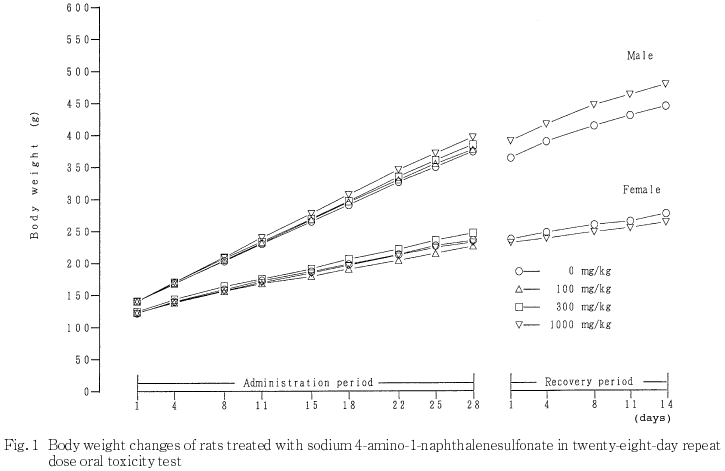
3. 摂餌量(Fig. 2)
投与期間および回復試験期間を通じて,雄の平均摂餌量では,溶媒対照群と比較して1000 mg/kg投与群の投与第8日の値が有意に増加したが,雌ではいずれの被験物質投与群においても有意差は認められなかった.
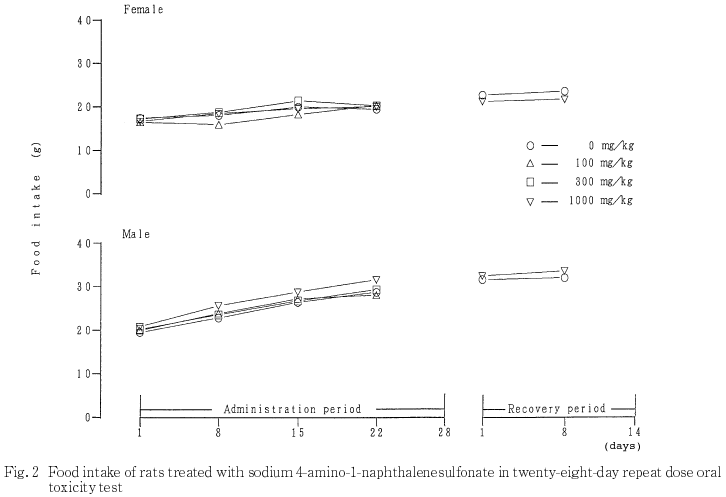
4. 尿検査(Table 1,2)
投与期間終了週の尿検査では,雄の1000 mg/kg投与群で3例,雌の300 mg/kg投与群で2例が尿中ビリルビン陽性であった.その他いくつかの項目で,投与期間終了週および回復試験期間終了週の検査において変化が散見されたが,いずれの検査項目においても,その出現例数あるいは程度に用量依存的な変化は認められず,溶媒対照群と被験物質投与群との間に被験物質投与に起因したと考えられる明らかな差は認められなかった.
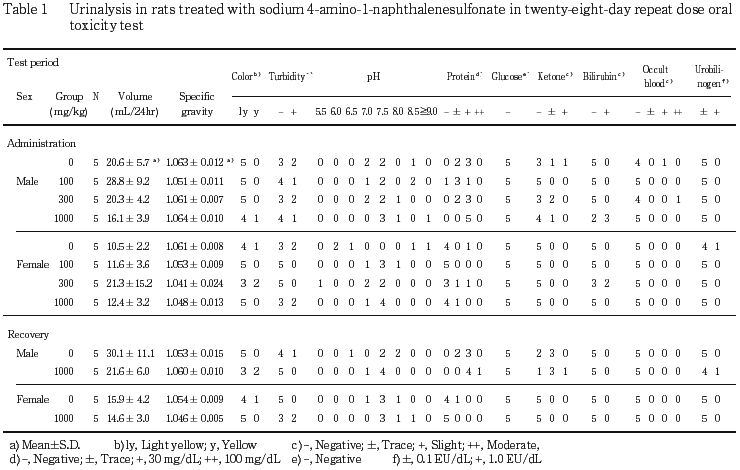
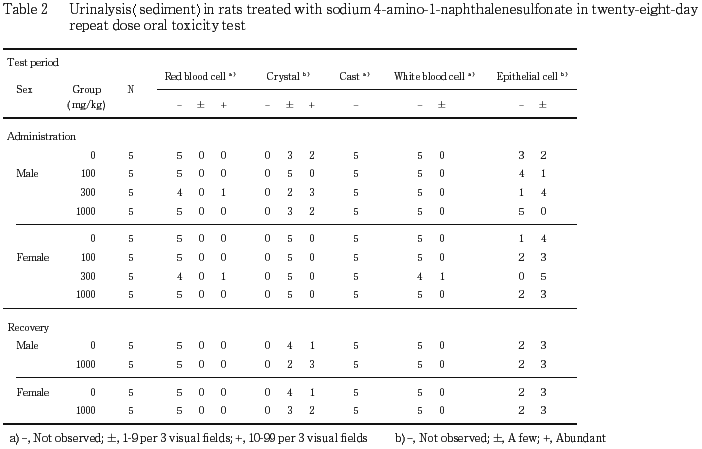
5. 血液学検査(Table 3)
投与期間終了時の血液学検査では,雌雄において,いずれの検査項目にも溶媒対照群と被験物質投与群の間に有意差は認められなかった.
回復試験期間終了時の検査では,1000 mg/kg投与群の雄で血色素量およびヘマトクリット値が有意に減少し,活性部分トロンボプラスチン時間が有意に短縮した.また,雌では白血球数が有意に減少した.
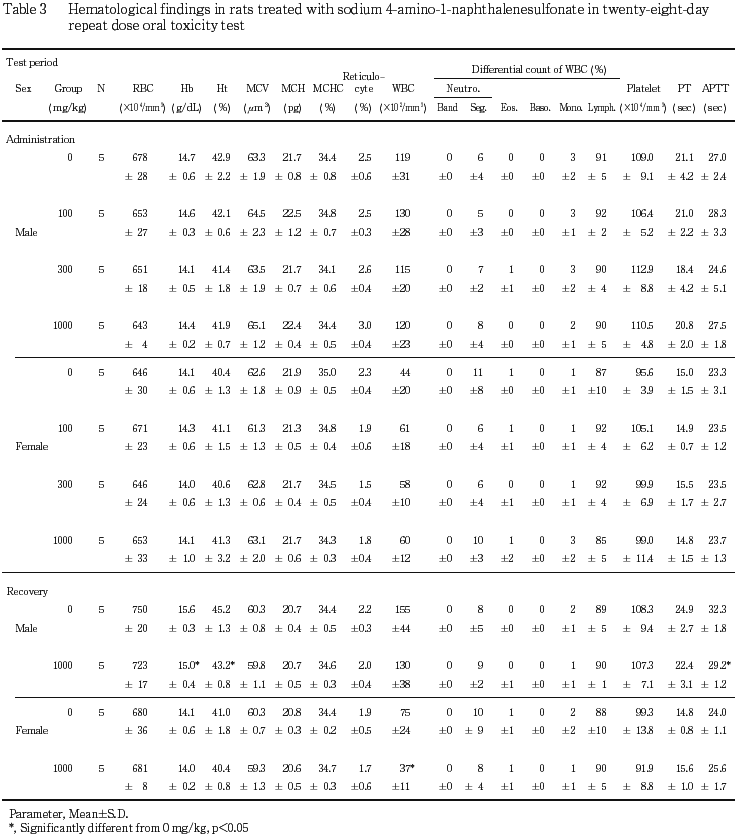
6. 血液生化学検査(Table 4)
投与期間終了時の血液生化学検査では,溶媒対照群と被験物質投与群の間に,雄では100 mg/kg投与群のカルシウム濃度,300 mg/kg投与群の総蛋白濃度が有意に低下し,雌では300 mg/kg投与群の無機リン濃度が有意に上昇したが,いずれも用量依存性のある変化ではなかった.また,雄の1000 mg/kg投与群のGPT活性に有意な上昇がみられ,雌の1000 mg/kg投与群ではクレアチニン濃度およびカルシウム濃度の有意な上昇および,GPT活性の上昇もみられた.
回復試験期間終了時の検査では,1000 mg/kg投与群において,雄でナトリウム濃度およびGPT活性が有意に上昇し,カリウム濃度が有意に減少した.また,雌ではナトリウム濃度が有意に上昇した.
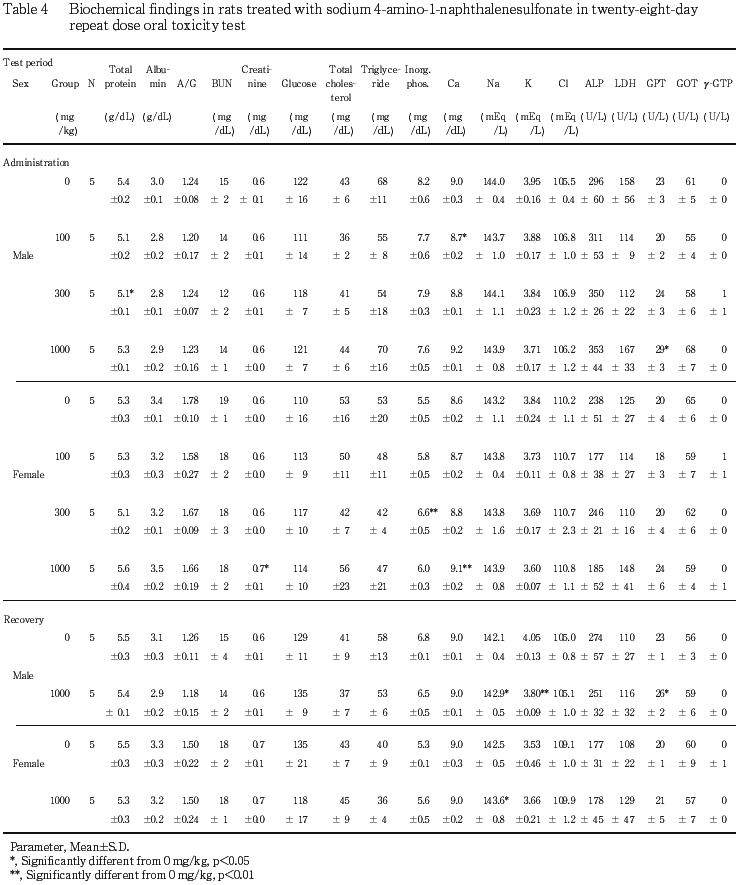
7. 病理学検査
1) 器官重量(Table 5)
投与期間終了時剖検例の器官重量では,雌雄において溶媒対照群と被験物質投与群の間で絶対重量,相対重量ともに有意差は認められなかった.
回復試験期間終了時剖検例の1000 mg/kg投与群における各器官の絶対重量は,雌の肝臓に有意な減少がみられた.また,相対重量は,雄の精巣および雌の肝臓で有意に減少し,雌の腎臓で有意に増加した.
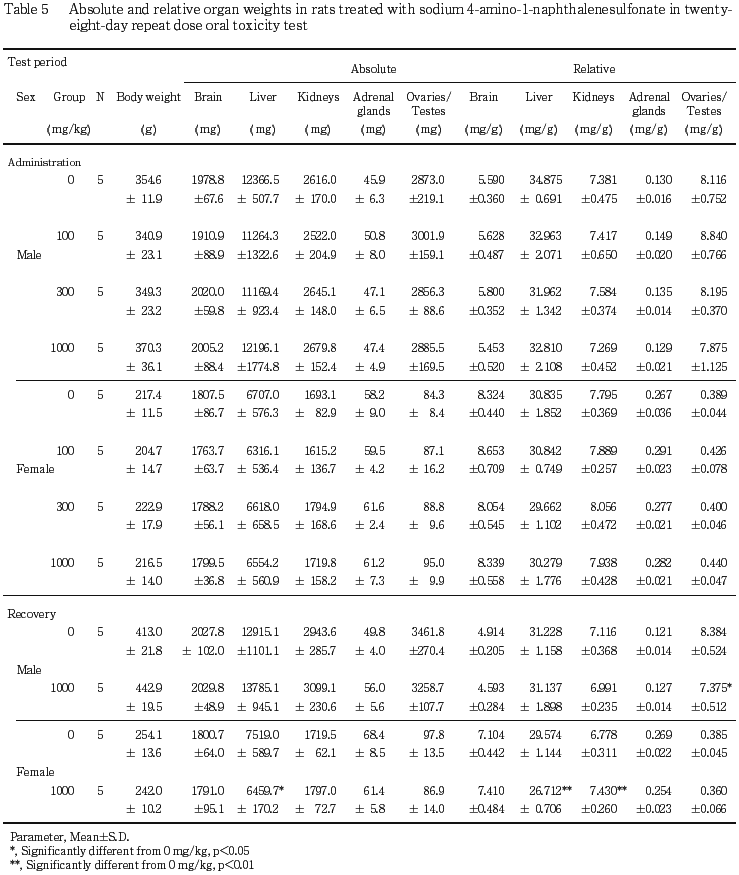
2) 剖検所見
投与期間終了時および回復試験期間終了時剖検例の剖検所見では,肺,腎臓,肝臓,副腎,下顎リンパ節および皮膚において変化が散見されたが,雌雄とも被験物質投与に起因すると思われる明らかな変化はなかった.
3) 病理組織学所見
投与期間終了時剖検例の肝臓では,雌雄の溶媒対照群および1000 mg/kg投与群に門脈周囲性の脂肪化がみられたが,両群間に頻度および程度の明らかな差はなかった.また,肉眼的に陥凹部がみられた300 mg/kg投与群の雄1例では組織学的に巣状壊死が認められ,淡色領域がみられた同群の雌1例では,門脈周囲性の脂肪化のほかに異常はみられなかった.脾臓では,雌雄の溶媒対照群および1000 mg/kg投与群の全例に髄外造血がみられ,雌の両群の全例に褐色色素沈着が認められたが,両群間に頻度および程度の差はなかった.
腎臓では雄の溶媒対照群および1000 mg/kg投与群の各4例,雌の両群の各3例の皮質に好塩基性尿細管がみられ,雌の両群の各2例の皮髄境界部に鉱質沈着が認められたが,両群間に頻度および程度の明らかな差はなかった.また,溶媒対照群の雄1例に嚢胞がみられ,1000 mg/kg投与群の雄1例に腎盂の拡張がみられた.さらに,肉眼的に皮質に嚢胞がみられた100 mg/kg投与群の雄1例は,組織学的にも嚢胞が確認されたほか,皮質に好塩基性尿細管がみられた.
その他,脳,脊髄,心臓,副腎および坐骨神経に異常はなく,その他の肉眼的に異常がみられた器官にも被験物質投与に起因すると考えられる病理組織学的変化はなかった.なお,いずれの病理組織学所見にも統計学的に有意差は認められなかった.
回復試験期間終了時剖検例では,肉眼的に異常がみられた器官に,被験物質投与に起因すると考えられる変化はなかった.
考察
4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウムの100,300および1000 mg/kgを,雌雄のSprague-Dawley系(Crj:CD)ラットに1日1回,28日間にわたって反復経口投与した.
その結果,一般状態の変化として1000 mg/kg投与群の雌1例において,投与第19日に投与後,一過性の流涎が認められたが,それ以降にはみられなかったため被験物質の刺激性に基づく反応ではないと判断した.また,投与期間中の平均摂餌量では,1000 mg/kg投与群の雄で投与第8日の値が有意に増加したが,持続的な変化ではなく,いずれも偶発的なものと考えられた.
さらに,投与期間終了週の尿検査では,尿中ビリルビンが1000 mg/kg投与群の雄3例で,300 mg/kg投与群の雌2例で陽性となったが,用量依存的な変化ではなく,それに伴う血液生化学および病理学的変化もみられなかった.また,尿中ビリルビン測定の際,溶媒対照群を除く被験物質投与群で,ビリルビンの試験紙反応部分が通常とは異なる色調を示した.確認のため高用量群および低用量群の投与検体を試験紙に浸したところ,前述した色調と同様の変化が認められ,これを本試験で使用した尿分析機器でビリルビンを測定した結果,低用量群で10本中8本,高用量群で10本中10本が陽性であった.一方,本試験で使用した尿試験紙は,ビリルビン検出反応として2,4-ジクロルアニリンと亜硝酸ナトリウムで形成されるジアゾニウム塩に,ビリルビンが作用してアゾ色素を形成する反応を利用しており,被験物質が試験紙のジアゾニウム塩と反応して,アゾ色素を形成する可能性が高いことが考えられる.以上のことから,ビリルビンの陽性反応については,試験紙と尿中の被験物質あるいはその代謝物の反応による可能性が高く,被験物質投与に起因した変化ではないと判断した.
回復試験期間終了時の血液学検査では1000 mg/kg投与群の雌において,白血球数の有意な減少が認められたが,白血球の百分比には変化がみられず,それに伴う病理学的変化も認められなかった.また,投与期間および回復試験期間終了時の血液生化学検査では,1000 mg/kg投与群の雌雄にGPT活性の上昇がみられ,雄では有意差も認められた.これらの成績を当研究所において過去2年間に「既存化学物質の安全性点検事業」として行った,3試験の28日間反復経口投与毒性試験における雌雄の溶媒対照群の血中GPT活性と比較した結果,雌雄とも投与期間終了時のGPT活性は高値であり,被験物質投与に起因した所見である可能性が高いと判断された.その他,血液学検査,血液生化学検査および器官重量においても有意差が散見されたが,いずれも被験物質投与との関連が明らかではなかった.
以上の結果から,本試験条件下における4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウムの無影響量は,雌雄とも300 mg/kgであると判断した.
| 連絡先 |
| 試験責任者: | 大原直樹 |
| 試験担当者: | 松岡千明,森村智美,加藤博康,関 剛幸,
小島幸一,吉村愼介, 畔上二郎,稲田浩子,
三枝克彦, 安生孝子 |
| (財)食品薬品安全センター 秦野研究所 |
| 〒257-8523 秦野市落合 729-5 |
| Tel 0463-82-4751 | Fax 0463-82-9627 | |
| Correspondence |
| Authors: | Naoki Ohara(Study Director)
Chiaki Matsuoka, Tomomi Morimura,
Hiroyasu Katoh, Takayuki Seki,
Kohichi Kojima, Shinsuke Yoshimura,
Jiro Azegami, Hiroko Inada,
Katsuhiko Saegusa, Takako Anjo |
| Hatano Research Institute, Food and Drug Safety Center |
| 729-5 Ochiai, Hadano-shi, Kanagawa, 257-8523, Japan |
| Tel +81-463-82-4751 | FAX +81-463-82-9627 | |
 〕に溶解し,さらに,この20 %溶液を6および2 %(w/v)濃度となるように段階希釈して調製した後,褐色瓶に分注し,冷暗所に保管した.投与検体は,前日に冷暗所から取り出し,室温にもどしてから使用した.投与検体の調製は4あるいは6日間に1回の頻度で行った.なお,調製検体の安定性試験および含量試験を実施した結果,0.2および20.0 %(w/v)溶液中の被験物質は,冷暗所での6日間と,それに続く室温24時間は安定であり,また,投与検体中の被験物質の含量は,所定濃度の102〜105 %であることが確認された.
〕に溶解し,さらに,この20 %溶液を6および2 %(w/v)濃度となるように段階希釈して調製した後,褐色瓶に分注し,冷暗所に保管した.投与検体は,前日に冷暗所から取り出し,室温にもどしてから使用した.投与検体の調製は4あるいは6日間に1回の頻度で行った.なお,調製検体の安定性試験および含量試験を実施した結果,0.2および20.0 %(w/v)溶液中の被験物質は,冷暗所での6日間と,それに続く室温24時間は安定であり,また,投与検体中の被験物質の含量は,所定濃度の102〜105 %であることが確認された. ,コールターエレクトロニクス)により赤血球数(電気抵抗法),白血球数(電気抵抗法),血色素量(吸光度法),平均赤血球容積(電気抵抗法),および血小板数(電気抵抗法)を測定し,これらを基に平均赤血球血色素量,平均赤血球血色素濃度およびヘマトクリット値を算出した.また,血液の一部は塗抹標本とし,白血球分類(Wright-Giemsa染色)および網状赤血球比率(Brecher法)を求めた.なお, プロトロンビン時間および活性部分トロンボプラスチン時間の測定には, クエン酸ナトリウムを抗凝固剤として採血した血液を用いて,光散乱検出法(CA-3000,東亜医用電子
,コールターエレクトロニクス)により赤血球数(電気抵抗法),白血球数(電気抵抗法),血色素量(吸光度法),平均赤血球容積(電気抵抗法),および血小板数(電気抵抗法)を測定し,これらを基に平均赤血球血色素量,平均赤血球血色素濃度およびヘマトクリット値を算出した.また,血液の一部は塗抹標本とし,白血球分類(Wright-Giemsa染色)および網状赤血球比率(Brecher法)を求めた.なお, プロトロンビン時間および活性部分トロンボプラスチン時間の測定には, クエン酸ナトリウムを抗凝固剤として採血した血液を用いて,光散乱検出法(CA-3000,東亜医用電子 法),アルカリフォスファターゼ活性(パラニトロフェニルリン酸基質法),GOT活性(SSCC法),GPT活性(SSCC法),LDH活性(Wr
法),アルカリフォスファターゼ活性(パラニトロフェニルリン酸基質法),GOT活性(SSCC法),GPT活性(SSCC法),LDH活性(Wr blewski-La Due法),カルシウム濃度(OCPC法),無機リン濃度(モリブデン酸直接法),トリグリセライド濃度(GPO・DAOS法),γ-GTP活性(γ-グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリド基質法),A/G比(総蛋白濃度およびアルブミン濃度より算出)を測定した.また,全自動電解質分析装置(EA05,A&T)により,ナトリウム濃度(イオン電極法),カリウム濃度(イオン電極法),塩素濃度(イオン電極法)を測定した.
blewski-La Due法),カルシウム濃度(OCPC法),無機リン濃度(モリブデン酸直接法),トリグリセライド濃度(GPO・DAOS法),γ-GTP活性(γ-グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリド基質法),A/G比(総蛋白濃度およびアルブミン濃度より算出)を測定した.また,全自動電解質分析装置(EA05,A&T)により,ナトリウム濃度(イオン電極法),カリウム濃度(イオン電極法),塩素濃度(イオン電極法)を測定した.